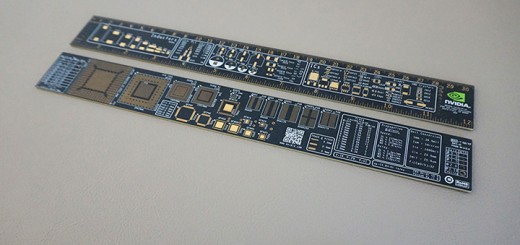VRを、顔に装着できるテーマ・パークだと考えてみてください。それは、視覚と聴覚で仮想世界を体験することであり、2Dスクリーンでちらつく映像を受動的に見るのとはわけが違う――と、SIGGRAPHで行われた講演のパネリストたちは言い、急速な成長を見せる新しい媒体向けの体験を開発する自分たちの仕事について語りました。
カリフォルニア州アナハイムで開催されたプロフェッショナル・グラフィックス会議では、満員の聴衆を前に、デジタル・エンターテイメント界から集結した先駆者たちがパネリストとして登壇しました。それぞれ、ウォルト・ディズニー・イマジニアリングのクリエイティブ・テクノロジ・リーダーであるベイ・ヤン(Bei Yang)氏、20世紀フォックスの未来研究者であるテッド・シロウィッツ(Ted Schilowitz)氏、SpacesのCEO兼共同創立者であるシラーズ・アクマル(Shiraz Akmal)氏、Baobab StudiosのCTO兼共同創立者であるラリー・カトラー(Larry Cutler)氏です。
このディスカッションは、Digital Cinema Societyの共同創立者であるジェームス・メイザース(James Mathers)氏による巧みな司会で進行されました。
VRにおける最大のリスクとは「リスクを取らないこと」
パネリストたちは、今こそVRでリスクを取るときだと主張しました。歴史的に名高いブランドが過去のテクノロジ革命で採用に失敗して凋落していったように、今リスクを冒さない企業は後れを取ることになるでしょう。
シロウィッツ氏は次のように述べています。「これまでの栄光の上にあぐらをかいていると、取り残されてしまう。最大のリスクは、新しいことを自ら試そうとしないことです」
言うまでもなく、VRは、最新技術によってサイエンス・フィクション・ファンタジーから初期の産業へと飛躍したものです。製薬から製造まで、幅広い分野の企業が新しいVRの導入を進めています。こうした状況を受け、今年のSIGGRAPH会議では、VR業界の前進を期待させる多彩なテクノロジが紹介されています。
これは、映画やゲームにおける従来のストーリーの伝え方が、ユーザーをデジタル世界へと引き込むメディア向けに再検討される必要があることを意味します。「人々が体験し始めたVRの真の能力の1つは、それがフラット・スクリーンによるメディアではないということです」と、シロウィッツ氏は言い、VRはユーザーが体験したいと思う空間感覚を生み出す、と付け加えました。「つまりユーザーは、本質的にテーマ・パークを顔に装着するようなものです」
ユーザーの心の準備を促す
最大の課題の1つは、ほとんどの人が一度も体験したことのないメディアによって伝えられるストーリーを受け入れられるよう、ユーザーを導くことです。たとえば、新しいもの好きの映画ファンなら、スクリーン上で機関車の映像が自分たちに向かって飛び出してくれば、これまでにない体験を試してみようと考えるかもしれません。
ヤン氏は次のように述べています。「その体験がどういったものか、自分たちがどのようなことをやろうとしているのかを、人々が理解できるようにすることが非常に重要です。たとえば、私が素晴らしいホラー作品を作ったとしたら、それを何の説明もなく誰かに押し付けるべきでしょうか?その人は心的外傷後ストレス症候群になる可能性だってあるわけでしょう」
そこで、遊園地から貴重な教訓が得られます。たとえば、ディズニーは、誰もが乗り物に乗る前にその怖さを知ることができるよう配慮しています。それは、人々が耐えられない乗り物に乗らずにすむようにするためだけでなく、楽しさを共有できない人に友達が楽しんでいる様子を見てもらえるようにするためでもあると、ヤン氏は説明します。
ビデオゲームが道を示す
ビデオゲームからも、別のインスピレーションが得られます。
VRデザイナーもゲーム・デザイナーと同様に、どの体験の要素がインタラクティブで、どれがそうでないかをユーザーが理解できるようにする必要があります。また、もう1つの教訓として、仮想世界では、ユーザーはストーリーよりも体験の方に関心を示す場合が多いということがいえます。
Spacesは、自社のモバイル・アプリのヒット作である「Dragons VR」の開発において、どのテスターもストーリーには注意を払わず、別世界の中にいることにひたすら感動を覚えるということに気付きました。「だから、当社はストーリーを取り払いました。単にドラゴンを飛ばせることだけがテスターの望みでしたから」と、アクマル氏は言います。
フラット・スクリーンを忘れ、スキー場を感じる
VRのストーリーは、新たな方法でユーザーが主導できる必要があります。たとえば、スキー場のゲレンデを滑走する場合、誰も逆方向に滑る人はいませんが、モーグル・コースで同じルートを通る人もいないことがわかります。
「一人ひとりの体験はある程度異なるでしょう」と、シロウィッツ氏は説明します。

 Chrome
Chrome Firefox
Firefox Opera
Opera Safari
Safari IE
IE